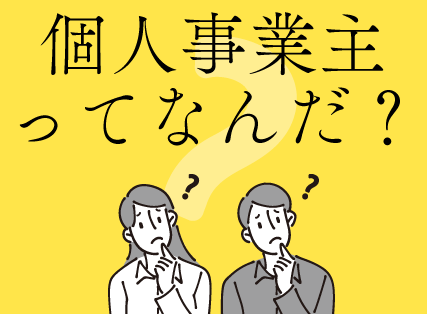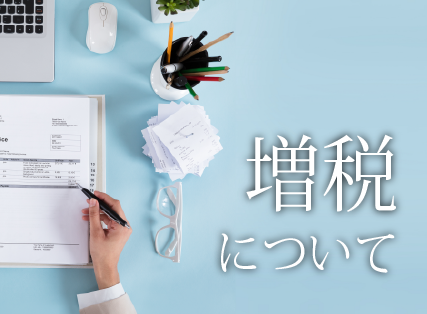2023年10月1日から始まったインボイス制度。消費税の取引処理がどのように変わったのか、免税事業者と課税事業者の違い、適格請求書(インボイス)の仕組みを整理します。
インボイス制度で何が変わったのか
2023年10月1日から、取引における消費税額を正確に把握するために、インボイス制度が導入されました。これについては「大増税だ!」という意見もあれば、「特に変わらない」という意見もあり、賛否が分かれています。
インボイス制度導入の背景
1989年4月、消費税が初めて導入された際に国民の反発があり、「小規模事業者は納税義務を免除する」免税事業者制度が採用されました。取引で受け取った消費税を納めず自分の利益にできる「益税」という仕組みです。
インボイス制度の目的は、この「益税」をなくすことにあります。
インボイス前とインボイス後の違い
インボイス前(2023年9月30日まで)は、年間売上1000万円以下の事業者(免税事業者)は、報酬に消費税10%を上乗せして受け取り、そのまま自分の利益としていました。
インボイス制度導入後の3つのパターン
- 取引先から消費税を受け取り、税務署に納める(課税事業者登録済み)
- 取引先から消費税分をもらえなくなる(免税事業者のまま)
- 免税事業者のままでも、取引先の判断で消費税分をもらい続けられる
このように、インボイス制度導入後は取引先や登録状況によって、消費税分の扱いが変わります。
インボイス(適格請求書)とは
インボイスとは、国が認めた形式で発行された「適格請求書」のことです。2023年10月1日以降、認められていない請求書を受け取った企業は、その消費税を経費計上できなくなりました。
企業会計への影響
経費にできないと利益額が増え、結果的に法人税負担が増えるため、企業は「インボイス発行事業者」との取引を優先するようになります。
インボイス発行事業者になる条件
インボイスを発行できるのは課税事業者に限られます。免税事業者だった人が登録すると、売上1000万円以下でも課税事業者になります。
免税事業者と課税事業者の違い
これまで年間売上1000万円以下の事業者は免税事業者として消費税の納付が免除されていましたが、インボイス制度では「消費税を受け取りたければ課税事業者登録が必要」となりました。
インボイス制度は増税なのか?それとも変わらないのか?
インボイス制度の導入により、免税事業者が消費税分を受け取れなくなるケースが増えました。ただし、取引先が免税事業者との取引でも消費税を上乗せして支払う場合は変化はありません。したがって、影響は事業者ごとに異なります。