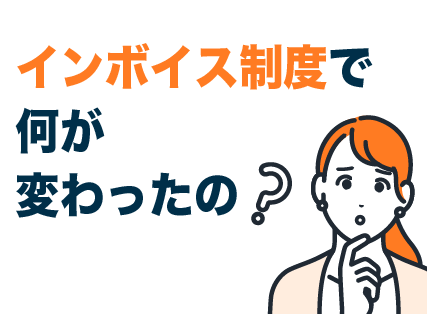1989年導入の消費税は、1997年に5%、2014年に8%、2019年に10%へ。なぜ増税が話題になるのか、背景と影響を整理します。
消費税の基本とこれまでの推移(概要)
普段の買い物で商品の価格に上乗せして支払う「消費税」。1989年に初導入、その後1997年5%、2014年8%、2019年10%へと引き上げられてきました。本記事では、なぜ増税が話題になるのかを分かりやすく整理します。
何のために増税するのか(増税の目的)
増税は家計の可処分所得を圧迫しますが、国が税制を動かす目的は大きく3つあります。
1.景気の安定化(マクロ安定化)
好景気では消費が過熱し物価が上がるため、増税で加熱を抑える。逆に不況時は減税で家計や企業の負担を軽減するなど、景気の振幅を和らげる役割があります。
2.格差の是正(再分配)
所得に応じて負担を調整し、高所得層からの税収を低所得層や公共サービスへ充当して格差を緩和します。
3.財源の確保(公共サービスの原資)
社会保障、公共インフラ、行政運営(公務員給与等)を賄うための安定財源を確保します。
最近の増税・制度変更(主なトピック)
1.たばこ税・所得税・復興特別所得税の延長(2024年4月)
2024年4月に増税・延長が実施(内容は制度ごとに異なる)。
2.自賠責保険料の賦課金引き上げ(2023年4月)
保険料のうち賦課金が引き上げ。家計や事業の維持費に影響します。
3.インボイス制度(2023年10月スタート)
適格請求書(インボイス)方式に移行。インボイスがない仕入は仕入税額控除が不可となるため、実質的に負担増となる事業者も出ます。
4.防衛費財源に伴う法人税の上乗せ検討
防衛費確保のため、法人税に4〜4.5%程度の上乗せを検討する不課税方式案が示されています。
5.今後見込まれる見直し
2025年:結婚・子育て資金一括贈与特例の廃止/2026年以降:教育資金一括贈与特例の廃止、相続税の延長、退職金課税強化、厚生年金支給減額などの議論も。
背景:少子高齢化と政策・負担のサイクル
少子高齢化で社会保障費が肥大化。高齢層の有権者比率が高まると高齢者向け政策が優先され、若年層の負担が増加。若者の可処分所得が減り、出生数の低下につながり、さらに少子高齢化が進むという悪循環が懸念されます。
色々な意見(メリット・デメリット)
インボイスを巡る事業者の立場の違い
免税事業者は登録番号取得のため課税事業者化が必要となるケースがあり、税負担増や売上減懸念で反対の声が出やすい。一方、もともと課税事業者の企業は負担構造の変化が少ない一方、事務負担の増加が課題に。
消費税のメリット
- 世代を問わず広く公平に徴収しやすい(偏在が小さい)
- 購入時に課税されるため脱税が困難で、安定的な税収を確保しやすい
消費税のデメリット・懸念
- 家計への負担感が強く、消費を抑制しやすい
- 税収の使途が不透明だと反発が強まる
総まとめ:消費税・増税をどう捉え、どう備えるか
消費税は景気調整・再分配・財源確保の柱。直近ではインボイスや各税制見直しで家計・事業への影響が拡大しています。時期と内容を把握し、価格転嫁・コスト見直し・家計管理・必要な制度申請など、できる対策を計画的に進めることが重要です。